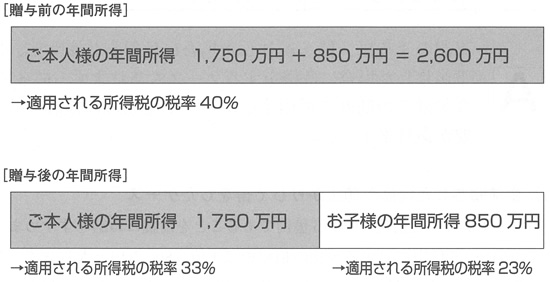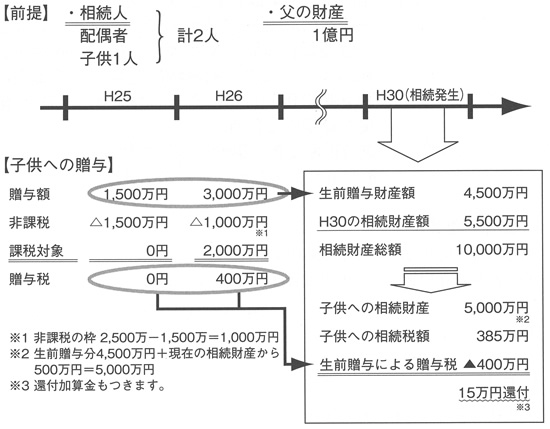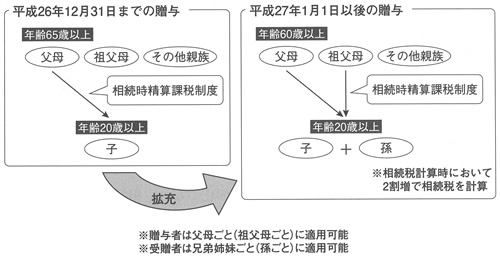1.「贈与」を正しく理解しよう
そもそも贈与とはどのようなことをいうのでしょうか。無償で財産を渡す、当たり前のことかもしれません。しかし贈与を正しく理解していないと思わぬところで税務当局から「実は贈与は成立していなかった」と指摘されるケスもあります。たとえば「名義預金」はその代表例といえます。子供名義の口座にお金を移したものの、子供はそのことをまったく知らず、口座自体も親が管理してい
るような場合には、たとえ親の意思で子供にお金をあげたという認識でいてもそのお金は実質的に親のものとされてしまいます。これでは相続対策をしたつもりがまったく効果がなかったことになってしまいます。
2.「贈与」は民法で定められている
「贈与」は民法549条で次のように定められています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
条文によると、当事者の双方が意思を表示し意思が合致することにより贈与が成立するとあるため、書面によって贈与契約を締結した場合には契約時に贈与が成立することになります。また、贈与は必ず’しも書面が必要というわけではなく口頭でも成立しますが、書面によらない贈与の場合には現実に財産を引き渡した等のタイミングで贈与が成立することになります。
3.税務当局に否認されないI贈与」とは
税務当局に否認されない贈与の成立は次の3つのポイントが重要となります。
(1)「あげた」という贈与側の意思表示があること。
(2)「もらった」という受贈側の受諾認識があること。
(3)もらった人がその財産を自ら利用、運用、管理している実績があること。
以上の3点については後目立証できることが重要となります。たとえば立証できる形跡として次のようなことがポイントになります。
・頚貯金等
→口座開設書類等には名義人本人が自署しているか。名義人本人が住所・氏名変更手続きや自ら出金した実績があるか。預金通帳・印鑑を名義人本人が保管しているか。
・上場株、投資信託等
→買付・売付の実際の指図人は誰か。配当金の実際の受取人は誰か。
・全財産共通
→贈与契約書を作成し自署押印しているか。贈与税の申告をし、自ら贈与税を納付しているか。